【地四国】全国の八十八ヶ所霊場一覧
地四国とは

そもそも四国八十八ヶ所霊場とは何?という方は下記をまずご覧ください。
さて、1200年前に弘法大師が開創した四国八十八ヶ所霊場ですが、弘法大師の教えが全国に広まるにつれ、多くの人が四国八十八ヶ所を訪れるようになりました。
しかし、昔の人々にとって四国は遠すぎる場所でした。そこで、自分達の地元で四国八十八ヶ所霊場を模した霊場を作り始めました。
新四国、準四国、准四国、写し四国と言う呼び方をするところもありますが、一般的には地四国と呼ばれます。
地四国は全国に広がりました。下記の地四国リストを見ればわかりますが、多くは江戸〜明治期、中には平成になってから開創されたものもあります。
衰退してしまったところもあると思いますが、現代でも多くの地四国が国内に残っており、巡拝する人達がたくさんいます。
ここではこの地四国を紹介したいと思います。公式または内容が記載されているサイトがある場合はリンクを付けておきますので、四国まではなかなか行けないと言う方はお近くの地四国を巡拝してみてはどうでしょうか?
全国の地四国一覧
北海道・東北
2006年にできたばかりの霊場です。総距離は3000㎞を超えます。5月〜10月まで開場。
昭和初期に開創。8㎞ほどで結願できる。
昭和初期に開創。以前は津軽観音八十八ヶ所霊場と呼ばれていた。
-
釜石八十八ヶ所(岩手県)
震災後、復興に向けて動いている。
-
陸中八十八ヶ所(岩手県)
1891年に開創。現在は霊場としての活動はしていない。
-
福島八十八ヶ所(福島県)
1992年にできた霊場。
-
北国八十八ヶ所(東北全域)
関東
1995年開創。関東地方一都六県に渡る霊場。
1920年に開創された草津市の霊場。四国八十八ヶ所各札所の土を石仏の下に埋めてあるという。
250年前に観寛光音という僧侶により利根川沿いに開創。
-
新四国埼東八十八ヶ所(埼玉県)
1798年開創。
-
北足立八十八ヶ所(埼玉県)
1898年開創。廃寺になっていたりするところもある現在は霊場としての活動はしていない。
-
新四国四箇所領八十八ヶ所(東京都・埼玉県)
1841年に開創されたが、現在は霊場としての活動はしていない模様。
1755年に開創。開創当時は御府内(江戸四宿内)にあった。現在は移転した寺院もあるがほぼ23区内で完結する。
-
南葛八十八ヶ所(東京都)
-
荒川辺八十八ヶ所(東京都)
文化年間(1800年代初頭)に開創されたとされる。
-
荒綾八十八ヶ所(東京都)
-
南葛新四国八十八ヶ所(東京都・千葉県)
1910年開創。江戸川区を中心に一部は千葉県に札所がある。
-
豊島八十八ヶ所(東京都)
1907年開創。北区や板橋区など7区に札所が点在する。現在は活動していない。
-
多摩八十八ヶ所(東京都)
1823年に開創され、後に衰退した武玉四国八十八ヶ所を元に1936年に作られた。
- 山内新四国八十八ヶ所(東京都)
安政年間(1855-1860)に開創された青梅市愛宕山周辺の霊場。
1934年開創。青梅市中心に一部は飯能市など埼玉県にも札所がある霊場。
-
玉川八十八ヶ所(東京都・神奈川県)
開創時期不明だが明治時代初期には既にあった。その後廃寺などもあり1973年に整備されている。世田谷区、大田区を中心に横浜市、川崎市にまたがる霊場。
-
吉橋大師講八十八ヶ所(千葉県)
1807年にできた下総四郡八十八ヶ所を元に1841年までに再編された。船橋市、八千代市を中心にした霊場だが現在では活動していないようである。また、いくつかの神社も札所になっているのが特徴。
-
中郷新四国八十八ヶ所(千葉県)
-
千葉寺八十八ヶ所(千葉県)
1754年に開創。
-
上総八十八ヶ所(千葉県)
詳細不明。
-
上総国市原郡八十八ヶ所(千葉県)
1785年開創。市原市内中心に札所がある。廃寺が多く、現在は活動していないようだ。
1821年開創。廃寺になったり大師像がなくなったりしているところがある。
-
東国八十八ヶ所(神奈川県)
1936年に開創。横浜市を中心に札所がある。現在は活動していない模様。
中部・関西
明治期には活動していたがいつ出来上がったものかは不明。総距離伊豆半島内444㎞でシアワセ遍路と呼ばれ、現在では観光の目玉の一つになり活動している。伊豆は弘法大師の修行の場であった。
1930年開創。伊豆市修善寺温泉周辺で毎年11月7日から9日まで桂谷八十八ヶ所巡りが開催される。
大正時代に開創。
- 甲斐八十八ヶ所(山梨県)
詳細不明だが甲斐八十八ヶ所観音霊場とも言う。一部廃寺。これとは別に1980年にテレビ山梨が作った甲斐百八霊場というものもある。
- 伊那諏訪八十八ヶ所(長野県)
1691年に開創された古い霊場。61年毎にご開帳があり、次回は2038年の予定。
1809年に開創。知多半島を巡る総距離194㎞の霊場。「歩いて巡礼知多四国」というイベントも毎年開催されているようだ。
- 覚王山八十八ヶ所(愛知県)
明治から大正にかけて出来上がった。名古屋市千種区覚王山周辺を巡る小さな霊場。毎月21日の縁日の日に開催されるようだ。
1625年に開創。栄枯盛衰を経ながら今の形になったのは1964年。知多とともに愛知県二大霊場とされる。三河地方が中心の霊場。
- 大名古屋八十八ヶ所(愛知県)
1939年開創。戦前までは活動が活発だったようだが、現在は衰退しつつあるようだ。
1925年開創。尾張八十八ヶ所霊場とも呼ばれる。知多半島の霊場。開創当時の四国八十八ヶ所霊場会会長より四国直伝証をいただき作られた。専用の納経帳や納め札もある。
江戸時代後期に作られたが、その後衰退。1975年に復興した岐阜市を中心とした霊場。
- 大谷山八十八ヶ所(岐阜県)
専用の納経帳があるらしい。公式サイトは作成中。
1745年に開創。島である佐渡は四国に行くのが困難のため作られたとされる。
1989年に作られた比較的新しい霊場。専用の納経帳もあり活発に活動しているようだ。
1851年頃開創とされる。総距離130㎞。敦賀市と美浜町中心の霊場。
1827年開創。成就山周辺に札所があり、総距離3㎞という小さな霊場。
1863年開創。総距離280㎞。伊賀市、名張市中心の霊場。毎年春にお山開き法要を行う。
1971年開創。三重県全域に札所がある。
江戸中期に開創。廃寺や無住寺もあるが活動は活発な模様。
江戸中期に開創。摂津国とは大阪府北中部と兵庫県南西部あたりのことでここを中心に札所がある。
中国・四国
江津市都野津町の遠見山を中心に札所がある。昭和初期に開創されたようだ。
- 美作八十八ヶ所(岡山県)
- 赤磐八十八ヶ所(岡山県)
- 児島八十八ヶ所(岡山県)
- 倉敷八十八ヶ所(岡山県)
1843年開創。こちらも倉敷市を中心とした霊場。総距離40㎞なので2〜3日で結願できる。
1804年頃開創。1時間程度で結願できる小さな霊場。
1860年に開創された福山市の霊場。当時は川口村と呼ばれた場所で総距離は8㎞。
寛政年間(1789-1800)に開創。
1926年開創。4時間半で結願できると言う。
1912年に開創された島四国。総距離84㎞。
- 箕島八十八ヶ所(広島県)
- 神石高原八十八ヶ所(広島県)
- 駅家八十八ヶ所(広島県)
1918年開創。広島市を中心とした霊場。平和公園の原爆供養塔を番外霊場としている。
1744年に開創された島四国。神島(こうのしま)は四国と形が似ているため、四国に倣って作られた。総距離29㎞なので頑張れば1日結願も可能。
- 高瀬八十八ヶ所(山口県)
1822年開創。周南市にある仙石岳周辺。四国八十八ヶ所の各寺の御本尊を同様に安置し、また各寺の土をその下に埋めたそうです。
- 秋穂八十八ヶ所(山口県)
1898年開創。総距離163㎞の霊場。
- 新四国曼荼羅霊場(四国全域)
1989年に81の寺院と7つの神社、合計88の寺社によって構成された霊場。四国4県全域に渡る。
上記粟島と同じ三豊市の荘内半島にある霊場。旧暦3月21日(弘法大師ご入定の日)には大勢で巡拝する。
観音寺市伊吹島にある霊場。他の島々と同様旧暦3月21日に島四国と称して島内を巡る風習がある。
- 瀬居八十八ヶ所(香川県)
開創時期は不明で江戸、明治など諸説あるようだ。かつては離島であったが瀬戸大橋もあり現在は島ではないが島四国の一つ。
1686年に開創された古い霊場。愛知県の知多四国八十八ヶ所、福岡県の篠栗八十八ヶ所とともに日本三大新四国霊場とも呼ばれる島四国。弘法大師が修行をした島であり、他とは違うという意味もあり元四国とも呼ばれている。
詳細は下記参照↓
- 讃岐一国八十八ヶ所(香川県)
讃岐(香川県)のみで完結する霊場で、1929年に開創された。
江戸期に開創。四国中央市川之江地区にあり、四国八十八ヶ所の寺の名前を刻まれた石仏が点在する。
1921年開創。新居浜市内にあり、寺だけでなく小祠の札所もある。
江戸中期には既にあったらしい。今は専用の納経帳もある。
江戸時代には活動していたが、開創時期は不明。今治市内の霊場。現在はあまり活動していないようだ。
1957年開創。今治市周辺の霊場。毎年4月第4金曜日〜日曜日に巡礼する習わし。
200年以上の歴史がある島四国霊場。旧暦3月21日に島の住民の多くが巡礼を始め、お接待もある。
ここも200年以上前に開創された島四国。4月第3日曜日に巡礼があり、お接待も行われる。
開創時期不明も周辺の島同様江戸期に開創されたと思われる。旧暦3月21日に巡礼が行われる。
こちらも詳細不明。巡礼は旧暦3月21日。
こちらも詳細不明。巡礼は旧暦3月21日。
1915年に開創されたと伝わる。
詳細不明の島四国。
- 風早八十八箇所(愛媛県)
江戸期に開創。毎年4月20日と21日に巡礼が行われる。島を一周する30㎞の遍路道。
毎年春にお大師巡りウォーキングが開催され、他島同様お接待などもあるようだ。
八幡浜地四国霊場とも呼ばれる。1849年開創。総距離3㎞ほど、山の周りの札所を巡礼する。
江戸期に開創された霊場。
詳細不明。ネットで何もヒットしないということは活動していないことと思われる。
詳細不明。上記と同じ卯之町にある。
1807年に開創された島四国。お接待や善根宿の風習が残る、総距離63㎞の道のり。春には3日間の縁日が毎年開催される。
九州
弘法大師ご入定1500年を記念して1984年に開始された。九州全県を巡拝する大きな霊場。
- 篠栗八十八ヶ所(福岡県)
1835年から続く福岡県糟屋郡篠栗町の霊場。弘法大師が修行した地とされる。総距離約50㎞。
江戸時代中期から後期にかけて開創された西山という山にある霊場。
- 六ヶ嶽新四国八十八ヶ所(福岡県)
- 宗像新四国八十八ヶ所(福岡県)
宗像市、福津市にある霊場。東部霊場と西部霊場に分かれている。幕末に開創され、1902年に再編成され、その後東部と西部それぞれ88ヶ所に分かれている。
- 粕谷北部新四国八十八ヶ所(福岡県)
1880年開創。ここも含め福岡県の霊場は大正時代前後に千人団という団体参拝組織を作り、歩いて巡拝する千人参りが盛んであったという。
- 筑前大島八十八ヶ所(福岡県)
明治時代に開創。ここも千人参りが盛んであったという。
- 島郷四国八十八ヶ所(福岡県)
- 福岡市新四国八十八ヶ所(福岡県)
戦前に開創された。名前通り全て福岡市内で完結する。
- 筑紫四国八十八ヶ所(福岡県)
筑紫野市、大宰府市にある霊場。戦後頃盛んであったと言われているようなので、開創は少なくても戦前以前。
- 糸島八十八ヶ所(福岡県)
糸島西部八十八ヶ所霊場と糸島東部八十八ヶ所霊場に分かれている。1952年に開創。
- 遠賀川川西八十八ヶ所(福岡県)
1903年に開創された。毎年3月25日〜30日が巡礼日とされる。
- 那珂川八十八ヶ所(福岡県)
- 帆柱新四国八十八ヶ所(福岡県)
- 三井四国八十八ヶ所(福岡県)
1903年開創。旧三井郡にある霊場。一時期は札所が増えて分割されたが現在は活動していないようだ。
- 浅ヶ部八十八ヶ所(宮崎県)
高千穂町浅ヶ部地区にある霊場。1835年に四国八十八ヶ所の各寺院の土を持ち帰って開創された。旧暦1月21日、3月21日、7月21日にはお接待がある。
- 宮野浦八十八ヶ所(宮崎県)
1819年開創。約12㎞で結願できる。旧暦3月21日には宮野浦八十八ヶ所大師祭が開かれている。
1855年に熱病の蔓延を抑えるために開創された。神社も含まれる。
1893年に開創。
1929年開創。長崎市茂木地区の霊場。御朱印は東長崎商工会茂木支所にて保管されている。
- 五島八十八ヶ所(長崎県)
1886年に開創。寺院だけでなく、観音堂や地蔵堂が札所になっている。
詳細不明。佐賀市内に全ての札所がある。これとは別に佐賀恵比寿八十八ヶ所巡りというものが存在する。
- 神埼八十八ヶ所(佐賀県)
詳細不明。神崎市の霊場。
- 有田八十八ヶ所(佐賀県)
明治期に開創。
1926年開創。栄枯盛衰があり、1987年に保存会が設立された。
大正時代に開創。近年廃れていたが2014年に復興した。
- 佐伯八十八ヶ所(大分県)
台湾
実は台湾にもあったのです。1925年開創。日本統治時代が終わった1945年まで運営されていました。四国八十八ヶ所霊場のご本尊を彫った石仏を札所に置いていたそうです。
詳しくは下記をどうぞ。
旧吉野村は現在の花蓮県になります。布教所は現在は慶修院という寺院になっています。日本統治時代に創設されたこの霊場は布教所の敷地内に散在する形で石仏を安置し、巡拝できるようになっていました。現在はまとめられています。
韓国
実は韓国にもあったそうですが、日本統治時代のものを残すという考えがあまりないためか、研究は進んでおらず、実態は不明ですが、いくつかの石仏が残されているそうです。
地域に根付く地四国

全国各地に多くの地四国がありますが、江戸時代から人口が急増した東京都周辺、それから四国八十八ヶ所が根付く瀬戸内周辺の県が多いのが見て取れます。
特に愛媛県の多さは特筆すべき部分で、島四国と呼ばれる島内で完結する地四国が多いのも特徴です。
瀬戸内には島が多いこと、さらに小さな島内で完結するので手軽にご利益が得られるとあって人気を博したようです。
これらの島四国の多くは旧暦3月21日など春頃に巡礼が行われ、お接待などもあるようで、島内のお祭り的な感じになっているようです。
また島四国を巡礼するお遍路さんのことを島遍路と呼びます。
上記に列記した地四国以外にもかつてはもっと多くの地四国がありました。
今回調べてみましたが、ネット上にほとんど情報がないものは掲載していませんし、またその存在すらも忘れ去られているものも多いと思います。
長い時を経て廃れてしまうのは仕方ないですが、中には近代になって開創されたり再興されたりしているところもあります。少なくても現代に形だけでも残っているものは今後も残ってほしいものです。
ちなみに私は東京に住んでいますので、南葛、御府内、豊島、荒川辺などは多くの札所となる寺院を訪れています。
南葛八十八ヶ所霊場だけは結願しました。皆様もまずは地元に近い霊場に足を向けてみてはいかかでしょう。そしていつかは四国八十八ヶ所霊場を巡礼してみてください。
→ 歩き遍路日記を最初から読みたい人はこちら【歩き遍路1日目】
---お知らせ---
本を出版しました。この本は用語集でもなく、遍路の作法や基礎知識のガイドブックでもありません。意外と知らない歩き遍路のちょっとしたコツをまとめています。
初めて歩き遍路に行く人にぴったりな内容です。この手の情報をまとめているサイトや本はまずありません。是非チェックしてみてください。
何かありましたらご連絡ください。
 |
中高年のための四国八十八ヶ所歩き遍路50日モデルプラン【電子書籍】[ 竹本修 ] 価格:1,430円 |
![]()
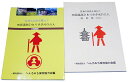 |
★新版★第12版★四国遍路ひとり歩き同行二人地図編★新版★第9版解説編のセットです。 価格:3,795円 |
![]()